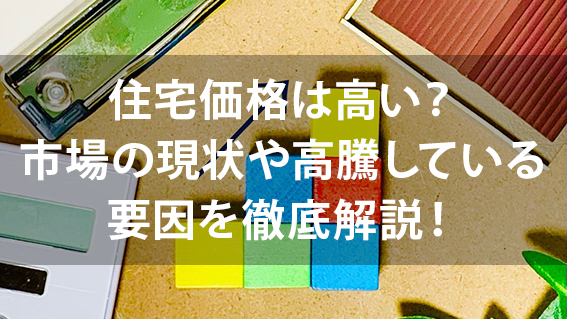- 近年、住宅価格が高騰している
- 住宅価格高騰の背景に需要増加、建材のコストアップなどがある
近年、住宅価格が高騰していると言われており、これから家を建てる方や家を購入する方の中で、悩まれている方もいるでしょう。とはいえ、住宅市場の具体的な現状や価格が高騰している理由がわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、住宅市場の現状に加え、価格高騰の要因や将来の展望について詳しく解説します。
さらに、記事の後半では、購入者視点で見た住宅価格についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
総合的な注文住宅の相場を知りたい方はこちらから→注文住宅の相場は?家を建てる時の必要な費用は?
住宅市場の現状

住宅価格が高騰している要因を解説する前に、まずは住宅市場の現状から見ていきましょう。
ここでは、住宅の平均価格と費用、注文住宅を建売住宅の価格比較に加え、土地と家の価格関係について詳し解説します。
住宅の平均価格と費用
住宅価格については、エリアや家の広さなどによって異なるものの、住宅金融支援機構が発表している「フラット35利用者調査」から読み取ることが可能です。
| 土地付き時 注文住宅 | 建売住宅 | マンション | 中古戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 4,694.1万円 | 3,719.0万円 | 4,848.4万円 | 2,703.6万円 | 3,156.9万円 |
| 首都圏 | 5,406.1万円 | 4,342.9万円 | 5,327.7万円 | 3,340.1万円 | 3,518.0万円 |
| 近畿圏 | 4,893.8万円 | 3,713.0万円 | 4,973.9万円 | 2,523.6万円 | 2,775.6万円 |
| 東海圏 | 4,693.9万円 | 3,151.1万円 | 4,434.9万円 | 2,316.7万円 | 2,220.7万円 |
| その他 | 4,151.0万円 | 2,947.5万円 | 4,018.5万円 | 2,149.8万円 | 2,546.6万円 |
引用:「住宅金融支援機構[フラット35利用者調査2022年度]」 より
あわせて読みたい:家を建てる時の必要な費用は?注文住宅の相場価格
注文住宅と建売住宅
先の表の通り、土地付き注文住宅と建売住宅を比べると、エリアによって金額差はあるものの、約1,000万円のひらきがあります。
注文住宅では、間取りや住宅設備を自由に選べることから、施主の希望やこだわりによって、どうしても金額が高くなってしまうのです。
一方、建売住宅については、あらかじめ決められた間取りや設備となっていることから、注文住宅と比べると費用が抑えられているのが特徴です。
あわせて読みたい:注文住宅と建売住宅の違い
土地と家の価格関係
先述の通り、土地付き注文住宅と建売住宅とでは、約1,000万円もの差があり、注文住宅のほうが高いです。とはいえ、土地付き注文住宅の場合、土地代が高いのか、家代が高いのか疑問に思われる方もいるでしょう。
実際、費用の内訳を見てみると、以下の通りです。
| 建設費 | 土地取得費 | |
|---|---|---|
| 全国 | 3,194.6万円 | 1,499.5万円 |
| 首都圏 | 3,117.9万円 | 2,288.2万円 |
| 近畿圏 | 3,133.4万円 | 1,760.4万円 |
| 東海圏 | 3,394.4万円 | 1,299.5万円 |
| その他 | 3,223.8万円 | 927.2万円 |
引用:「住宅金融支援機構[フラット35利用者調査2022年度]」 より
上表の通り、土地代よりも建設費のほうが高い傾向にあります。とくに、首都圏では土地代が高い傾向にあることから、土地取得費が2,288.2万円となっており、全国平均よりも高い数値となっているのが特徴です。
住宅価格高騰の要因

近年、住宅価格が高騰していると言われており、これから家を建てようと思っている方や、家を購入しようと思っている方の中で、どれくらいの予算に設定するべきか悩んでいる方もいるでしょう。
さらに、そもそもなぜ、住宅価格が高騰しているのかが気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは、住宅価格が高騰している理由について、詳しく見ていきましょう。
住宅価格が高騰している理由
住宅価格が高騰している背景には、さまざまな理由が考えられます。
たとえば、ウッドショックも住宅価格高騰の原因といえます。ロシアがウクライナに侵攻したことがきっかけで、木材をロシアから輸入できなくなってしまい、国産材などの代用品を使うようになりました。
そして、そもそも輸入材よりも国産材のほうが、建材費用が高いことから、結果的に建築コストが高くなったのです。
新築住宅と中古住宅
首都圏では、新築マンションの供給が減っている一方、需要が増えていることから、マンションの価格が高くなっています。そして、それに伴い、中古マンションの価格も比例するかのように高くなっているのです。
ただ、戸建て住宅については、コロナ禍をピークにゆるやかに価格が落ちてきています。とはいえ、資材や燃油代の高騰、人件費が高くなったことなどの理由から、土地価格は下がっているものの、建設コストが高くなっているので、実質はあまり変動がないといえるでしょう。
なお、中古住宅についても、新築同様に高くなっています。その背景には、原油価格の高騰に加え、人件費が上がったことが挙げられます。
あわせて読みたい:ハウスメーカーの坪単価ってどれくらい?
住宅ローン金利の影響
その他の理由として、住宅ローンが低金利で借りられる点が挙げられるでしょう。
一般的に、家を購入するときや建てるときは、住宅ローンを利用します。ただ、金利によって、総返済額が変わることから、金利が高いときほど、購入を躊躇ってしまう方が多いでしょう。
しかし、日本銀行のマイナス金利政策により、住宅ローンの低金利化が進み、以前よりも住宅ローンを利用しやすくなったのです。さらに、新型コロナウイルスの蔓延により、自宅で過ごす時間が増えたことから、家づくりを検討する方が増えました。
低金利と相まって、家づくりを検討する方が増えたことから、住宅の需要が高まり、結果的に建築費用が高くなったといえるでしょう。
あわせて読みたい:住宅ローンはいくら借りられる?
住宅価格の将来展望

住宅価格の推移と予測
ここでは、住宅価格の推移について、国土交通省が発表している「不動産価格指数」をもとに詳しく見ていきましょう。
| 不動産価格指数 (住宅総合) | 不動産価格指数 (戸建て住宅) | |
|---|---|---|
| 2008年12月 | 101.0 | 96.7 |
| 2009年12月 | 98.6 | 97.2 |
| 2010年12月 | 101.0 | 103.0 |
| 2011年12月 | 99.6 | 102.1 |
| 2012年12月 | 99.4 | 102.2 |
| 2013年12月 | 102.2 | 112.3 |
| 2014年12月 | 103.7 | 116.6 |
| 2015年12月 | 106.0 | 124.9 |
| 2016年12月 | 108.1 | 130.0 |
| 2017年12月 | 110.7 | 138.1 |
| 2018年12月 | 113.1 | 145.3 |
| 2019年12月 | 113.7 | 149.6 |
| 2020年12月 | 117.2 | 158.2 |
| 2021年12月 | 124.6 | 172.1 |
| 2022年12月 | 133.6 | 187.1 |
| 2023年12月 | 137.1 | 196.2 |
国土交通省は発表している不動産価格指数は、2010年の平均値を100としており、各年および月ごとに指数が示されています。
上表の通り、毎年、不動産価格指数が高騰していることがわかるでしょう。また、戸建て住宅については、2010年の基準値より、2023年12月の数値が約2倍となっています。
つまり、建設費用が高くなっていることを示しており、今後もますます価格が高くなる可能性があるでしょう。
住宅価格高騰の現状(2024年)
2023年12月現在では、2010年の数値よりも、約2倍の不動産価格指数となっています。ウッドショックやオイルショックに加え、人件費の高騰など、さまざまな要因によって建設コストが高くなっているのです。
なお、まだまだ住宅ローンが低金利であることから、住宅価格がどんどん高くなる前に家を建てたり、購入したりしようとする方が増え、需要と供給のバランスから、さらに住宅価格が高騰する可能性も少なくありません。
住宅価格が下落する可能性は?
ここまでは、住宅価格が高くなる理由や、これまでの推移に加え、今後高くなる可能性があることを解説しました。
しかし、住宅価格が下落する可能性を考えている人もいるでしょう。
人口減少に伴い、2024年以降は、空き家の増加に加え、世帯主の減少などの理由から、地方の不動産価格が下がっていく可能性があります。需要と供給のバランスが崩れると、地価が下がっていくので、土地代が下がることも珍しくありません。
また、低金利から通常の金利に戻ったときや、不動産関連の税制が改正されることで、さらに需要が低くなり、住宅価格が下がることもあるでしょう。
たとえば、日本銀行の政策により、金利が高くなれば、住宅ローンを利用する人が少なくなり、結果的に需要が減少することから、住宅価格が下がります。
そのほか、現状住宅ローン減税などの税制措置がありますが、そういった税制が悪い方向に改正されれば、住宅の買い控えがはじまり、需要と供給のバランスが崩れて、結果的に価格が安くなっていく可能性があります。
購入者の視点から見た住宅価格

これまでは、統計やデータを使って、住宅価格の現状や推移、将来の展望について解説しました。
実際、過去10年間で比較すると、どんどん住宅価格が高くなっていることがわかります。その背景には、建材のコストアップだけでなく、人件費や燃油代の高騰なども影響しているのです。
とはいえ、統計やデータではなく、購入者の視点から現在の住宅価格を見ると、どのような見方ができるのでしょうか。
ここでは、「住宅の購入の困難さ」「家の値段と生活費」「住宅価格高騰への対策」の3つをテーマに、細かく解説していきます。
住宅価格の高騰と購入の困難さ
近年、どんどん住宅価格が上がっているので、10年前と比べると、経済的に住宅購入が難しくなってきているといえるでしょう。
とくに、若者世代の場合、貯蓄や所得を考慮すると、住宅価格が高すぎるでしょう。そのため、金融機関や住宅ローン専門業者では、一般的な35年ローンだけでなく、40年や50年といった長期の住宅ローンを展開しはじめてきているのです。
ローンの借入期間が長くなれば、その分、毎月の返済額を抑えられるので、住宅価格が高くなっている昨今でも、購入できるといった仕組みです。
家の値段と生活費
住宅価格が高くなると、住宅ローンが同じ借入期間であれば、毎月の返済額が増えます。そのため、毎月の生活費を圧迫してしまい、食費や交際費など、ほかの生活費を抑える必要があります。
たとえば、食費や娯楽費であれば、節約できる可能性もあり、積極的に節約すれば、住宅ローンの返済額が高騰した分をカバーできるでしょう。
そのほか、インターネットや携帯電話などの固定費の見直しをおこなうことで、結果的に生活費を抑えることができ、住宅ローンの返済に充てることが可能です。
住宅価格高騰への対策
住宅価格が高騰している中で、購入者ができる対策として挙げられるのが、エリアの選定、延床面積の縮小です。
注文住宅の場合、土地代によって、総支払額が大きく変わることから、少しでも安い土地を選ぶことで、予算を抑えることが可能です。とはいえ、利便性や周辺環境も生活するうえでは重要な要素であることから、土地代とのバランスを考慮して検討することがポイントといえるでしょう。
また、延床面積を小さくすることで、建築コストを抑えることができます。たとえば、10年前のデータで比較すると、仮に同じ面積で家を建てた場合、建材などが高くなっていることから、建築費用に大きな差が出てくるでしょう。
しかし、延床面積を小さくすることで、使用する建材を減らすことができることから、結果的に建築費用を節約することが可能です。
まとめ:住宅価格は高騰している
近年、住宅価格は高騰しており、過去10年と比較すると、戸建て住宅については、2倍ほどの不動産価格指数となっています。
少子高齢化に伴い、家の需要が減るとはいえ、依然として住宅価格の高騰が続いています。しかし、昨今は40年や50年といった長期の住宅ローンを選択できるようになっており、そういったローン商品を利用することで、毎月の返済額を抑えることが可能です。
また、家の延べ床面積を小さくすることで、使用する建材の量を減らせることから、結果的に建築コストを抑えれるでしょう。
あわせて読みたい:注文住宅の補助金制度完全ガイド