注文住宅を新築する時、普段はあまり耳慣れない「登記」という手続きに行き当たり、戸惑う方も多いのではないでしょうか?登記は不動産を取得する際に避けては通れない手続きで、少なからず費用も発生します。こちらの記事では、不動産登記の種類や費用の相場について解説します。注文住宅を建てようと考えている方はぜひお読みになり、情報収集や資金計画に役立ててください。
不動産登記とは
そもそも「登記」とは何でしょうか?登記とは、個人や法人が所有する不動産・債権などの法律上の権利・義務を公開した帳簿(登記簿)に記載して公示し、それらを保護した上で取引の円滑化を図る日本の行政上の仕組みです。登記がないと、第三者に対して所有権を主張することができません。古くは紙の帳簿に直筆で記載されていましたが、現在では電子化されて申請・閲覧が容易になっています。
登記の中でも、不動産登記は以下のように定義されています。
不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
出典:法務省
次の項では、注文住宅を新築する際に必要な登記の種類をご説明します。
建物表題登記
特定の土地に初めて建物を建てた時に行う登記です。建物の所在地・家屋番号・構造・床面積などを表示して登記します。不動産登記法により、建物の完成から1か月以内に登記申請が必要であると定められています。
所有権保存登記
不動産の所有者・所有権を証明するための登記です。新築の注文住宅に対しては、建物表題登記に続いて所有権保存登記を行います。
所有権移転登記
既に所有されている不動産の所有権を取引・相続などによって移転させる時に行います。注文住宅の新築に先立ち土地を購入する場合、所有権移転登記が必要になります。
抵当権設定登記
住宅ローンを利用する場合に必要な登記です。この登記により、住宅ローンの貸主(金融機関)に抵当権があることを証明します。借主が住宅ローンの返済不能に陥った時、貸主は借主の不動産を差し押さえることができます。
抵当権抹消登記
住宅ローンの返済完了時や、借り替え時に行う登記です。返済完了時は単純に抵当権抹消登記のみを行い、金融機関から抵当権を抹消します。住宅ローンの借り換え時には、例えば金融機関A社からB社に借り換える場合、A社に対して抵当権抹消登記を行い、B社に対しては新たに抵当権設定登記を行うことになります。
注文住宅の登記費用の相場
不動産登記の種類を確認できたところで、次は登記費用について確認していきます。登記費用には主に以下の3種類があります。
- 登録免許税(収入印紙代)
- 依頼先の専門家に支払う報酬
- 書類の取得費・交通費・郵送費などの実費
このうち1は決まった数式で税金を算出しますので、特定の登記手続きに対する金額は同一です。主に差額が生じるのは2で、これは依頼先の土地家屋調査士や司法書士によって報酬金額が変わるためです。3は実務で発生する実費ですので、差額が出たとしても大きくはならない可能性が高いです。
では、次の項で具体的な金額を見ていきましょう。
新築注文住宅の登記費用はいくら?【50万円かかるのは本当?】
単刀直入にお伝えしますと、専門家に登記を依頼した場合、新築注文住宅の登記費用は30万円~50万円程度かかるのが相場です。以下の表に登記の種類と費用をまとめました。
【登記の種類と費用】
| 登記の種類 | 登録免許税 (収入印紙代)※ | 依頼先 | 報酬の相場 |
|---|---|---|---|
| 建物表題登記 | なし | 土地家屋調査士 | 8万円 |
| 所有権保存登記(建物) | 固定資産税評価額 ×0.4%(0.15%) | 司法書士 | 2万円~3万円 |
| 所有権移転登記(土地) | 固定資産税評価額 ×2.0%(1.5%) | 司法書士 | 3万円~5万円 |
| 抵当権設定登記 | 借入金額 ×0.4%(0.1%) | 司法書士 | 4万円~4.5万円 |
※登録免許税の( )内税率は以下の期限まで適用される軽減税率です。
土地:2023年3月31日まで
建物・抵当権:2024年3月31日まで
参考:土地家屋調査士報酬ガイド/司法書士の報酬と報酬アンケート/財務省/国税庁
登記の種類別に、登録免許税の金額をそれぞれシミュレーションしてみます。
所有権保存登記(建物)
新築の建物は完成時点では固定資産税評価額が未定ですので、各自治体が設定している「新築建物課税標準価格認定基準表」を参考にします。この基準表では1㎡あたりの単価が建物の構造別に算定されていますので、構造と床面積から固定資産税評価額を算出します。ここでは仮に東京の基準表を使用し、木造で38坪の建物で試算してみます。
38坪×3.3=125.4㎡(建物の床面積)
125.4㎡×102,000円/㎡=12,790,800円(固定資産税評価額)
12,790,800円×0.4%=約5万円
※軽減税率適用:約2万円
所有権移転登記(土地)
土地の固定資産税評価額は各自治体が独自に算定し、時価の70%程度とされています。仮に土地の時価が1千万円と仮定した場合、所有権移転登記の登録免許税は以下のようになります。
1千万円×70%(固定資産税評価額)×2.0%=14万円
※軽減税率適用:10.5万円
抵当権設定登記
抵当権設定登記は、借入金額を3千万円として試算します。
3千万円×0.4%=12万円
※軽減税率適用:3万円
登記費用合計
先に算出した所有権保存登記(建物)・所有権移転登記(土地)・抵当権設定登記の登録免許税の合計は以下の通りです。
5万円+14万円+12万円=31万円
※軽減税率適用:15.5万円
土地家屋調査士や司法書士といった、専門家に各登記手続きを依頼した場合の報酬を、合計してみます。
8万円+3万円+5万円+4.5万円=20.5万円
登記費用合計は
31万円+20.5万円=51.5万円
※軽減税率適用:36万円
固定資産税評価額や借入金額がシミュレーションより安ければ登記費用ももう少し安くなります。専門家に依頼した場合、このように登記費用の相場は合計で30万円~50万円程度はかかると想定しておくのがよいでしょう。
あわせて読みたい:家を建てる時の必要な費用は?注文住宅の相場価格
その他に必要な諸費用の相場

登記費用などの諸費用の合計は、建築総費用の10%程度が相場と言われています。建築総費用が3,000万円なら、そのうち諸費用は300万円程度になる計算です。
【建築費用の割合】
建築総費用(土地代は除く)=本体工事費(70%)+付帯工事費(20%)+諸費用(10%)
注文住宅にかかる諸費用は、主に土地購入関連・建物新築関連・住宅ローン関連の3種類に分かれ、金額はそれぞれの住宅で大きく異なります。こちらでは種類ごとの項目と概要をご説明します。(登記費用についての説明は前出ですので割愛します。)
土地購入関連
注文住宅にかかる諸費用のうち、土地の購入に関連する税金や仲介手数料についてご説明します。
印紙税(印紙代)
土地の売買契約書には以下の印紙の貼付が必要です。
【不動産売買契約書の印紙税】
| 契約金額 | 通常税率 | 軽減税率※ |
|---|---|---|
| 100万円超~500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円超~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
※2024年3月31日までに作成された10万円を超える不動産の譲渡契約書は、軽減税率が適用されます。
参考:国税庁
不動産取得税
不動産取得税は地方税で、納税先は都道府県になります。従来、税額は固定資産税評価額の4%でしたが、2024年3月31日までは以下のように軽減措置が取られています。
【従来】
固定資産税評価額×4%
【軽減措置】(2024年3月31日まで)
宅地:固定資産税評価額×1/2×3%
参考:総務省
不動産仲介手数料
土地の購入代金が400万円を超える場合、上限は「取引価格(税抜)×3%+6万円+消費税」です。
建物新築関連
注文住宅にかかる諸費用のうち、建物の新築工事に関連する費用や税金についてご説明します。
地鎮祭
工事を始める前の地鎮祭には、地域にもよりますが数万円程度の費用がかかります。
ご近所への手土産代
建築工事を始める前には、ご近所さんに挨拶回りをするのが通例です。お菓子などの手土産をお持ちし、面通しするとともに工事の騒音などで迷惑を掛けることに理解を得ておきましょう。
上棟式
上棟式には大工さんや工事関係者へのご祝儀・昼食代が必要になり、ご近所さんを呼んで餅まきをすることもあります。地域や施工会社・建築様式によって内容が大きく異なるほか、最近は上棟式を実施しない方も増えています。まずは施工会社に相談してみましょう。
大工さんへのお茶出し費用
工事が始まると、休憩時間に大工さんへお茶やお菓子を提供することもよくあります。施工会社によっては原則不要とされていることもありますので、確認してみましょう。
建築確認申請費用
建築確認とは、建築工事の開始前や完了後に、その建物が建築基準法や条例などに適合しているかを確認する作業です。確認作業は管轄の自治体や、自治体から指定された民間の検査機関が実施します。
建築確認は最低でも着工前と完成後の2回に行われ、建物によっては工事中も含めて3回行われます。建築確認申請費用は床面積によって変わりますが、合計で数万円程度の費用がかかります。以下に東京の例を記します。
| 床面積の合計 | 30㎡超~100㎡ | 100㎡超~200㎡ |
|---|---|---|
| 確認申請 | 9,400円 | 14,000円 |
| 中間検査申請 | 11,000円 | 15,000円 |
| 完了検査申請 | 11,000円 | 15,000円 |
参考:東京都都市整備局建築基準法関係申請・通知手数料
【建築確認の流れ】
建築確認申請(「建築確認申請書」の提出)→自治体・検査機関が書類で確認→「建築確認済証」の交付→着工→中間検査→中間検査合格証→完成→完了検査の申請→完了検査→「検査済証」の交付
建築工事契約時の印紙税
建築工事請負契約書には以下の印紙の貼付が必要です。(金額は土地購入の時と同じです。)
【不動産売買契約書の印紙税】
| 契約金額 | 通常税率 | 軽減税率※ |
|---|---|---|
| 100万円超~500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円超~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
※2024年3月31日までに作成された10万円を超える不動産の譲渡契約書は、軽減税率が適用されます。
参考:国税庁
不動産取得税
こちらも土地購入の時と税率は同じですが、新築住宅については固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。建物の固定資産税評価額は、新築購入価格の約60%が目安とされています。
【従来】
(固定資産税評価額-1,200万円)×4%
【軽減措置】(2024年3月31日まで)
(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
参考:総務省
住宅ローン関連
注文住宅にかかる諸費用のうち、住宅ローンに関連する費用についてご説明します。
金銭消費貸借契約書の収入印紙代
住宅ローンを組む時には金銭消費貸借契約書を交わします。契約書に貼付する印紙代は、多くの方が借入する1,000万円超~5,000万円以下の金額では2万円となります。
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 500万円超~1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 6万円 |
参考:国税庁
住宅ローン事務手数料
住宅ローンの事務手数料は、金融機関に対し住宅ローンの申込手続きの手数料として支払うものです。中には事務手数料が無料のこともありますが、ほとんどの金融機関では数万円以上の固定金額か借入額の1~2%程度を手数料として設けています。
ローン保証料
ローン保証料は、連帯保証人を付けずに保証会社に保証を依頼する場合に必要となります。無料にしている金融機関もあるほか、借入金額によって決めたり、金利に上乗せしたりするなどの設定方法があります。
団体信用生命保険料
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンの返済者が死亡・高度障害・ガンなどで返済不能な状態に陥った時に、保険会社がローン残高全額を金融機関に対して支払う仕組みです。これにより、残された家族は住宅ローンの負担なく同じ家に住み続けることができます。
民間の金融機関から住宅ローンを借入する場合、死亡・高度障害といった基本的な内容を保障する団信の保険料は金融機関が支払うため、返済者の負担は実質ゼロです。ただし、ガン特約・三大疾病特約などを付加して保障内容を充実させると、その分金利が高くなるのが通常です。
一方、フラット35の団信に加入した場合、借入金額が3,000万円ですと1年目の特約料は約10万円です。
火災保険料・地震保険料
一括で支払うと、長期的には最も安くなります。保険料は条件によって大きく変わりますが、目安としては1年に数万円かそれ以上となることが多いです。地震保険は単独の加入ができず、必ず火災保険とセットで加入することになります。
現在、火災保険の最長保険期間は5年です。火災保険は2015年の10月までなら最長で36年、2022年10月までは最長10年の保険期間で契約できましたが、2022年10月以降は改定により最長でも5年までの契約しか結ぶことができなくなりました。
これは近年大規模な自然災害が多発するようになり、保険会社が長期的な収支予測をすることが困難になったためです。
新築の注文住宅を建てたら火災保険・地震保険には必ず加入しましょう。長期の住宅ローンを組み、万が一自宅が火災や地震で焼失・損壊しても、住宅ローンの返済はなくなりません。
つなぎ融資の諸費用
つなぎ融資とは、住宅ローンの融資が始まるまでの費用を一時的に賄うための仕組みです。一般的に住宅ローンの融資は建物が完成して買主に引き渡されてから開始されます。しかしながら、住宅ローンの融資が始まる前に土地を購入し、建築費用は着工から竣工までの期間に数回に分けて支払うのが慣例です。
土地代や建築費用を自己資金で工面できる購入者は稀で、ほとんどの方はつなぎ融資を利用して住宅ローンの融資が始まるまでの出費に対応することになります。そして、住宅ローンの融資が始まったら、つなぎ融資を一括返済します。
つなぎ融資は無担保融資のため、住宅ローンよりも金利が割高なのが特徴です。つなぎ融資は住宅ローンとは別契約ですので、個別に事務手数料や収入印紙代(借入金額が1,000万円超~5,000万円以下の場合は2万円)も発生します。つなぎ融資で2,500万円を借入する場合、利子・事務手数料・収入印紙代の合計が20万円~30万円になることも珍しくありません。これは手持ちの現金から支払う必要があるので注意が必要です。また、工期の長いハウスメーカーでは融資期間が長くなるので、利子が高くなることも留意しておきましょう。
その他
注文住宅にかかる諸費用のうち、土地購入・建物新築・住宅ローン以外の費用についてご説明します。
転居費用
現在の居住地とは違う場所に注文住宅を新築する場合は1回の転居費用が、現在の住まいを一旦取り壊して注文住宅を新築する場合には2回の転居費用が必要となります。新居までが近距離であっても、家族3~4人分の引越なら1回で10万円以上の費用を想定しておきましょう。
仮住まい費用
現在の住まいを一旦取り壊して注文住宅を新築する場合には、解体費用の他に仮住まいの費用も必要になります。仮住まいの期間は工期に左右されますが、最も工期の早い鉄骨ユニット系のハウスメーカーなら2~3か月、それ以外の工法では4~6か月程度が目安です。工期の長さに合わせて、賃貸住宅やマンスリーマンションの利用を検討してみましょう。
家財の中で仮住まい中に使用する予定がない物は、トランクルームや貸し倉庫に一時保管しておくという手段もあります。
家財購入費
新築すると、新居に合わせて新しい家具や家電製品・生活用品の購入費用が発生します。一見大きな出費には見えないかもしれませんが、この費用も積もり積もると大きな金額になることがあります。

新築注文住宅の登記の流れ
最初の章では登記の種類についてご説明しましたが、ここでは登記の流れについて順を追ってご説明します。土地を購入し、住宅ローンを組んで新築の注文住宅を建てる場合を想定しています。
1.土地の購入~所有権移転登記
土地を購入したら所有権移転登記を行い、所有権を買主に移転します。
2.建物の完成~建物表題登記(完了まで1~2週間)
建物が完成したら、建物の存在を公示するために建物表題登記を行います。建物表題登記は建物の完成から1か月以内の登記申請が法律で義務付けられており、怠ると10万円以下の過料に処されるので注意が必要です。
3.建物の完成~所有権保存登記(完了まで1~2週間)
建物表題登記に続いて、建物の所有者・所有権を公示するために所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、事前に建物表題登記がされていないと申請できない仕組みになっています。
4.住宅ローンの利用~抵当権設定登記(完了まで1~2週間)
住宅ローンを利用するためには、貸主である金融機関に抵当権があることを証明するために、抵当権設定登記を行います。抵当権設定登記は所有権保存登記と同時に進めます。
登記費用を抑えることはできる?
登記費用を少しでも抑えるためには、ハウスメーカーに任せきりにしたり紹介された専門家にそのまま依頼したりせずに、少なくとも3社から相見積を取って金額を比較してみましょう。どこに依頼しても登録免許税は変わらないので、主に差額が出るのは報酬になります。報酬は土地家屋調査士や司法書士が独自に設定しているので、ある程度の相場はあるものの金額に開きが出る可能性があります。
注文住宅の登記は自分でできる?
登記手続きの申請は注文住宅の買主が自分ですることもできますが、ある程度の専門知識と法務局が開いている平日に十分な時間が必要で、間違いは混乱を引き起こすので推奨はできません。
【登記申請の流れ】
- 必要な書類を揃える(ハウスメーカー・不動産会社・自治体の役所や法務局から入手)
- 書類を作成する(登記申請書の記入・図面作成など)
- 法務局へ提出する
分からないことは法務局で教えてくれますし、事務作業や書類作成が得意なら買主が自分でできる事柄もありますが、あくまで自己責任となります。
なお、抵当権設定登記を債務者である買主が行うことは、銀行は原則として認めてくれません。余計なトラブルや不信感を招かないためにも、抵当権設定登記は銀行指定の司法書士にそのまま任せるのが無難です。
対照的に、住宅ローンの完済時に行う抵当権抹消登記は、時間があれば自分でする価値があります。
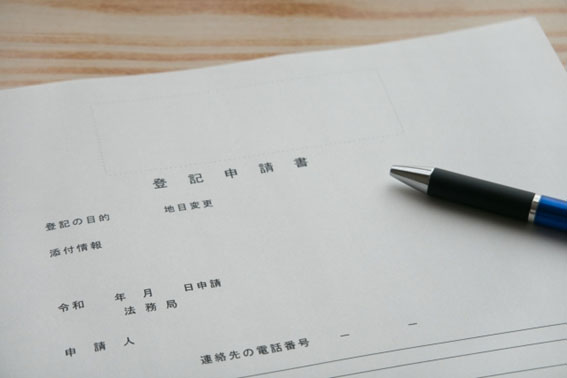
注文住宅の諸費用や総費用を把握する方法
注文住宅は一生に一度あるかないかの大きな買い物です。登記費用だけでも30万円~50万円程度かかる可能性が高く、登記費用を含めた諸費用の全体は、土地代を除く建物の建築総費用の約10%程度が相場です。結局のところ、注文住宅を建てるには、思い描くプランとそれに沿った全体の資金計画を立てることが非常に大切になってきます。
初めての注文住宅で多くの方が経験するのが、「何をどう始めていいかさっぱり分からない」ということです。かと言って、複数社の住宅展示場を1つ1つ見て回ると、見学や商品説明だけで膨大な時間がかかってしまいます。
そのような問題でお悩みの方には、「タウンライフ家づくり」の無料相談サービスがおすすめです。タウンライフ家づくりでは、希望事項を記入して複数のハウスメーカーに一括送信するだけで、各ハウスメーカーから以下の3つの提案書を入手できます。
- 間取りプラン
- 資金計画書
- 土地提案
提案書では希望に沿った間取りプランを提案してもらえるだけでなく、資金計画書では総費用や諸費用の概算が把握できます。土地の提案までしてもらえるので、自宅にいながらじっくりと各プランの比較検討ができ、時間を大きく節約できます。
まとめ
こちらの記事では不動産登記の種類や費用の相場について解説してきました。新築注文住宅の登記費用は30万円~50万円程度かかるのが相場で、依頼する専門家によって報酬に多少の差はありますが、買主が自分で登記申請手続きをするのはあまりおすすめできないという点が主なポイントです。
登記申請はハウスメーカーに完全お任せでも基本的に問題はありませんが、登記やそれ以外の費用について主体的に理解しておくことで、注文住宅という大きな買い物を合理的に進めることができるのではないでしょうか。
そして、注文住宅の構想を大きく前進させてくれるのが「タウンライフ家づくり」のサービスです。たったの3分で簡単に登録し、無料でご利用できますので、ぜひお役に立てて夢のマイホームを実現させてください。




