借入金利が軒並み超低金利時代の今、
金利はないに等しいとも言われますが、
実際に金利はどの程度支払額に影響するのでしょうか?
また、もし金利の影響が小さいのならば
どのように住宅ローンを選択すればいいのか考えてみたいと思います。
住宅ローンの総支払額を比較してみよう
まずは、金利と総支払額の関係を見るために
以下の条件で総支払額を比べてみます。
共通条件【3,000万円 35年返済 全期間固定】
金利条件【0.8%、1%、3%、5%】
※ ボーナス払いなし、元利均等返済
※ その他の諸経費は考慮していません
| 金利 | 毎月返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 0.8% | 8.2万円 | 3,441万円 |
| 1% | 8.5 | 3,557 |
| 3% | 11.6 | 4,850 |
| 5% | 15.2 | 6,360 |
※ 住宅金融支援機構ローンシミュレーションを使用
【参照】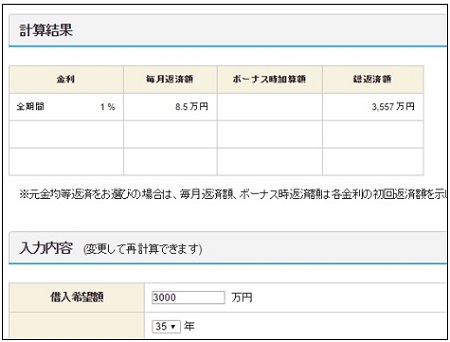
上記表では、5%と1%の総返済額の差は約2,800万円にも及びます。
この差は非常に大きく、この数字を見ると
金利は少しでも低いほうがいい、と考えてしまいがちです。
しかし、0.8%と1%の差額を見てください。
総支払額の差は約116万円です。
100万超という金額は決して小さい額ではありません。
しかし、毎月返済額で見るとその差は3,000円です。
金利差を頭に入れておけばともかく、
毎月の生活費の中では金利の恩恵を実感しにくい
というのが本音ではないでしょうか。
10年前に金利5%以上で住宅ローンを組んだ人が
借り換えをするならばその差を大いに実感できるでしょうが、
新規に借入を行う人が1%か、0.8%かを選択するのは難しいといえます。
なぜならば「金利は低いほうがいい=0.8%のほうがお得」とは言い切れないからです。
つまり、金利だけを決定要因として考えるのではなく、
事務手数料や保証料といったローン借入時の諸経費、
ローン商品によって異なる団体信用生命保険の内容などを、
複合的に考えて住宅ローンを選ばなければならないのです。
住宅ローン商品の傾向
最近の住宅ローンの傾向として、
低金利、かつ手数料も縮小傾向というのが挙げられます。
更にメガバンクや大手銀行でもインターネットバンキングを駆使して
ネット専用銀行に負けず劣らずの利便性を誇ります。
例えば、みずほ銀行は店頭での繰り上げ返済は有料ですが、
インターネットバンキングから行うと無料になります。
他にも、KDDIと三菱東京UFJ銀行が共同出資して設立した
インターネット銀行(じぶん銀行)は、契約書が不要であり、
申し込みから契約まで全てネットで完結するなど、
住宅ローンはどんどん進化しています。
あわせて読みたい:住宅ローンを繰り上げ返済してはいけない大きな理由とは
低金利時代はどのように住宅ローンを選ぶべきか
低価格化&多様化してきているといえる住宅ローン、
今後はどのように取捨選択していくべきなのでしょうか。
先ほど挙げたように利便性で選ぶ人、
やはり金利を重視する人など様々でしょうが、
私が提案したいのは「継続性」です。
例えば新築の家を購入しても、
将来リフォームが必要になるかもしれません。
リフォームは自分たちが住み続けるためものかもしれませんし、
中古住宅としての転売目的かもしれません。
住宅購入から何十年後は、以下のような多くの可能性が考えられます
- 自分たちが住み続けるための機能向上リフォーム、減築リフォーム等
- 子どもや孫が同居する二世代、三世代同居リフォーム
- 子どもが独立して手広くなったため賃貸併用住宅へのリフォーム
- 売却、もしくは保有しつつ賃貸へ出すためのリフォーム
このように、何らかの形でリフォームを行うことは多いでしょう。
その際に、住宅購入時と同じ金融機関を選ぶと何かとメリットがあります。
住宅ローンを返し終えたという実績をもってリフォームに臨むため、
審査や金利面でスムーズに事が運びやすいのです。
年齢が高じると、お互い気心が知れているというのも大きなメリットでしょう。
もちろん、新たな金融機関を探すというのも有効な手段です。
ただし、高齢になると体力や情報収入の面で
負担が大きい可能性は否めません。
まとめ
超低金利時代の今、
総支払に対して金利が及ぼす影響は小さいといえます。
そのためローンを絞り込めない、何を重視したらいいのか?
という人も多いと思います。
迷ってしまったときは、住宅購入時に
「何十年後、リフォームするとしたらまたこの金融機関とローンを組むかもしれない」
という目線で選んでみてはいかがでしょうか?




